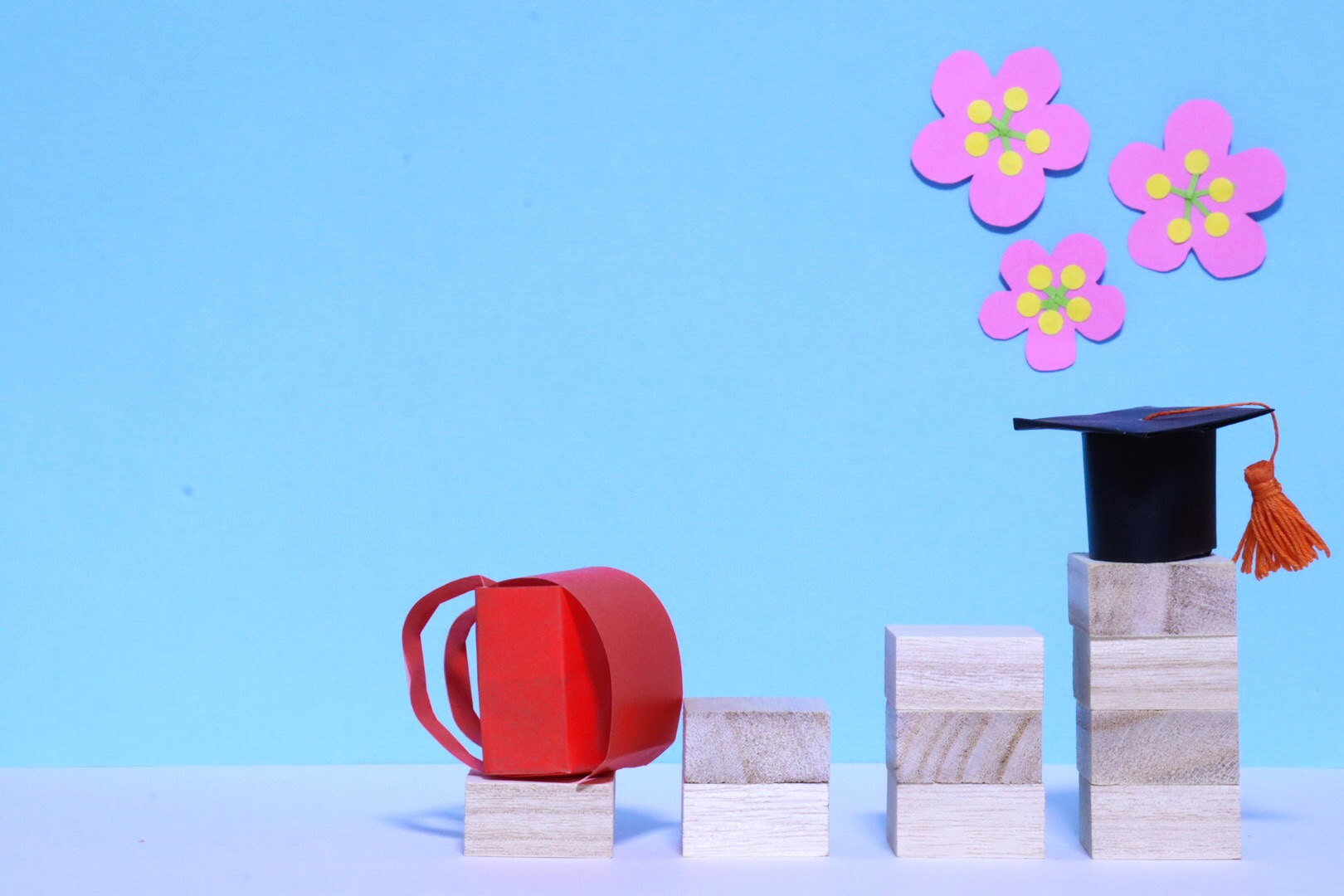すぐ謝る子供の心には「お母さんに嫌われたくない」「お母さんが怖い」というような心理が隠されています。
これはお母さんが叱る時に、つい叱りすぎてしまったり、叱ると怒るの違いが区別つかずに感情的に怒ってしまったりしている可能性が高いです。
一時的に親子の関係が崩れていると考えられます。
叱り方のポイントや親子関係が修復できる方法を実践して親子の絆を深めていきましょうう。
子育にはイライラがつきものですが、お母さんのイライラで子供の心に悪影響を与えてしまわないよう注意してください。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

子育てにイライラ!子供に暴言を言いいそうになったときの対処法
子育てにイライラして暴言を言ってしまう・暴言を言ってはいけないと思っているのにやめられない。こんなお...
-

子供の躾【2歳】わがままを言う理由とイヤイヤ期の正しい対処法
2歳の子供の子育てをしていると、所々で子供のわがままな行動が見られるようになります。2歳の子供のわが...
-

夜ご飯を食べない子供への対策!食べない原因とママにできる工夫
子供が夜ご飯を食べない事に頭を悩ませているママもいるのではないでしょうか。食事をしてくれないと栄養が...
-

子供の野菜嫌いは克服可能?野菜の摂取方法と子供の味覚について
子供が野菜嫌いだと、栄養面などが心配になっていしまい、少しでも野菜を摂取してほしいと考えます。...
すぐ謝る子供の心理の特徴
子どもの言い分を聞かずに怒られる時
友達同士のいざこざ、部屋を片付けない、出かける前なのに急がないなど子どもの行動に目を光らせてしまう時が生活の中にあります。予定通りに事が進まないときは怒りが沸点に達してしまい、ついつい大きな声を出して感情をあらわにしてしまいます。
結果だけを評価してしまうと自信をなくしてしまう
習い事で長い間時間をかけて成功した事、工作や絵などを頭の中で色々と想像し慣れないはさみやのりなどを使って出来上がった作品などを見て欲しくて持ってくることは無いでしょうか?
その時出来上がったものだけを評価して、それまでの過程を端折ってしまうと出来上がったものが自分にとって不出来な出来栄えだと認められず、親にも認められないと自信がなく謝ってしまうこともあります。
すぐ謝る子供の心理にはこんな思いが隠されている
親の愛を感じられない
起こってしまった事に対して理由も聞かず親の感情だけで怒られてしまうと子どもの言いたい事も封じられてしまい「自分のことを嫌っているんだ。」「親は自分のことを知ってくれない。」と親の愛が自分に向いて欲しく謝ることもあります。
何を言っても自分の気持ちを知ってもらえないと思っている
親というのは子どもよりも経験が多くたくさんの困難や成功を味わってきています。
自分も子どもも1人の人間で同じ経験をしても同じようにこなせるというわけではないのです。
頑張ってやっても共感を得られない
小さな子どもにとってはまだまだ初めての経験が多いものです。出来なくて当たり前なのですが、親が忙しい時や下に妹や弟がいる場合はついつい比較してしまい出来るだろうと期待をしてしまうものです。子どもも最後までやってみようと頑張っている時に、手を出して怒りながら親がやってしまうと今まで子どもがやってきたことに意味がなくなってしまい、頑張りを共感してもらえないとすぐに謝る子になってしまいます。
すぐ謝る子供の心理!自己否定、自尊心の低下に繋がりやすいので注意
我慢することが当たり前になってしまう
謝れば事が収まる方法を覚えてしまい、自分が悪くなくても我慢をしてすぐ謝ることが出来てしまいます。そうなると問題の解決にもならず相手によっては問題を擦り付ける人も出てきます。我慢というのは重ねる毎に麻痺してしまい当たり前になってしまうことがあります。
自分自身の存在を認められなくなる
すぐに謝る心理というのは、自分の思いを閉じ込めて自分の意見を出さずその場を終わらせてしまうことが多いでしょう。
その一言で自分の思いを出せない状況が続くと誰にも共感を得ることが出来ないとイ意固地になってしまい自分を攻めてしまうこともあります。
責任逃れしてしまう
他の視点からの心理ですが、親が自分の気持ちを聞かず何もわかってくれないから何も言わない。
どうせ頑張っても何もほめてもらえないからとりあえずやるけど頑張らない。
親への恐怖心からすぐ謝る子供にしないためにポジティブな叱り方を理解しよう
怒りにまかせ過去の事と一緒にしない
子どもというのは何度言っても同じように出来なかったり失敗をするものです。しかし毎日接している親もそのたび穏やかでいられないのもわかります。子どもは努力を怠っているわけでもなく、失敗してやろうと思ってしているわけではありません。前回のことを引き合いに出して叱ってしまうと「何回やっても出来ない」と自分に自信がなくなってしまいます。
わかりやすく叱る
怒りに任せて色々と言葉を並べても子どもにとっては親の声と雰囲気が怖く何も響いていない場合があります。大人でも聞いて覚えるということは何個も覚えられず難しいのです。その時に起こった出来事だけをわかりやすく具体的に視覚からの情報を交えて教えてあげるといいでしょう。子どものタイプによっては再現して教えたほうがわかりやすいタイプの子どももいます。
子どものすべての行動まで否定しない
今出来なくて叱られていることを他の事に結びつけて叱るのはやめましょう。例えば出かけるまでの時間に間に合いそうに無い時、朝起きるのが遅いから、夜遅くまで起きているから、早くご飯を食べないからなどさかのぼってしまうのは間違えです。間に合うように頑張れば良いだけなのです。それに対しての努力を教えるだけなのです。
子供がすぐ謝るのは親子関係が崩れている証拠!親子関係を修復するための方法
叱り方が子どもにとって良くないと感じたら謝ること
自分の行動を見直しいけなかったことを詳しく伝える
叱ると怒るの違いを理解し、感情的になっていたならそれを伝えましょう。気持ちを知ろうとしようと努力をしていなかったなら素直に伝えましょう。
どうしてそのような行動をしたのかを伝える
「仕事が忙しすぎて気持ちが焦っている」「時間に間に合うように行動し楽しい時間を過ごしたいから気持ちが落ち着かなかった」等怒る理由は色々あると思います。これをしっかり伝えないと愛されていないから怒られたんだと自信が無い子どもになってしまいます。
子どもの気持ちに共感する
怒られて不安になった気持ちや、怖かった気持ちに共感し気持ちをわかってあげましょう。心の消化が完了すると気持ちの切り替えや愛されているという気持ちになり自分を肯定できるようになるでしょう。
叱ってしまったけど子どもへの愛は変わらないと言葉にして伝えましょう
最後はきちんと言葉にして、手を取り合ったり、抱っこしたりして大事だという気持ちを言葉と態度で示しましょう。