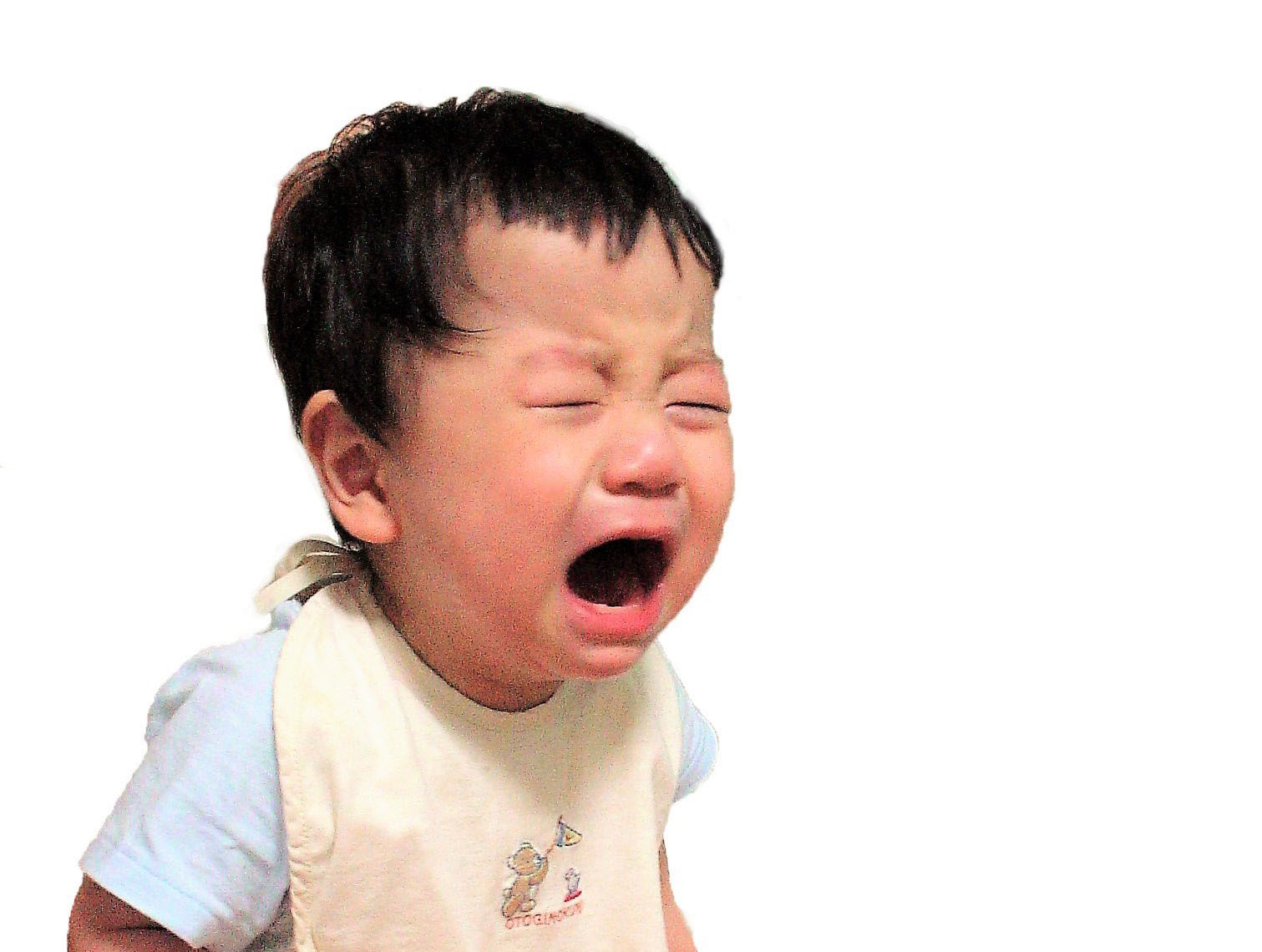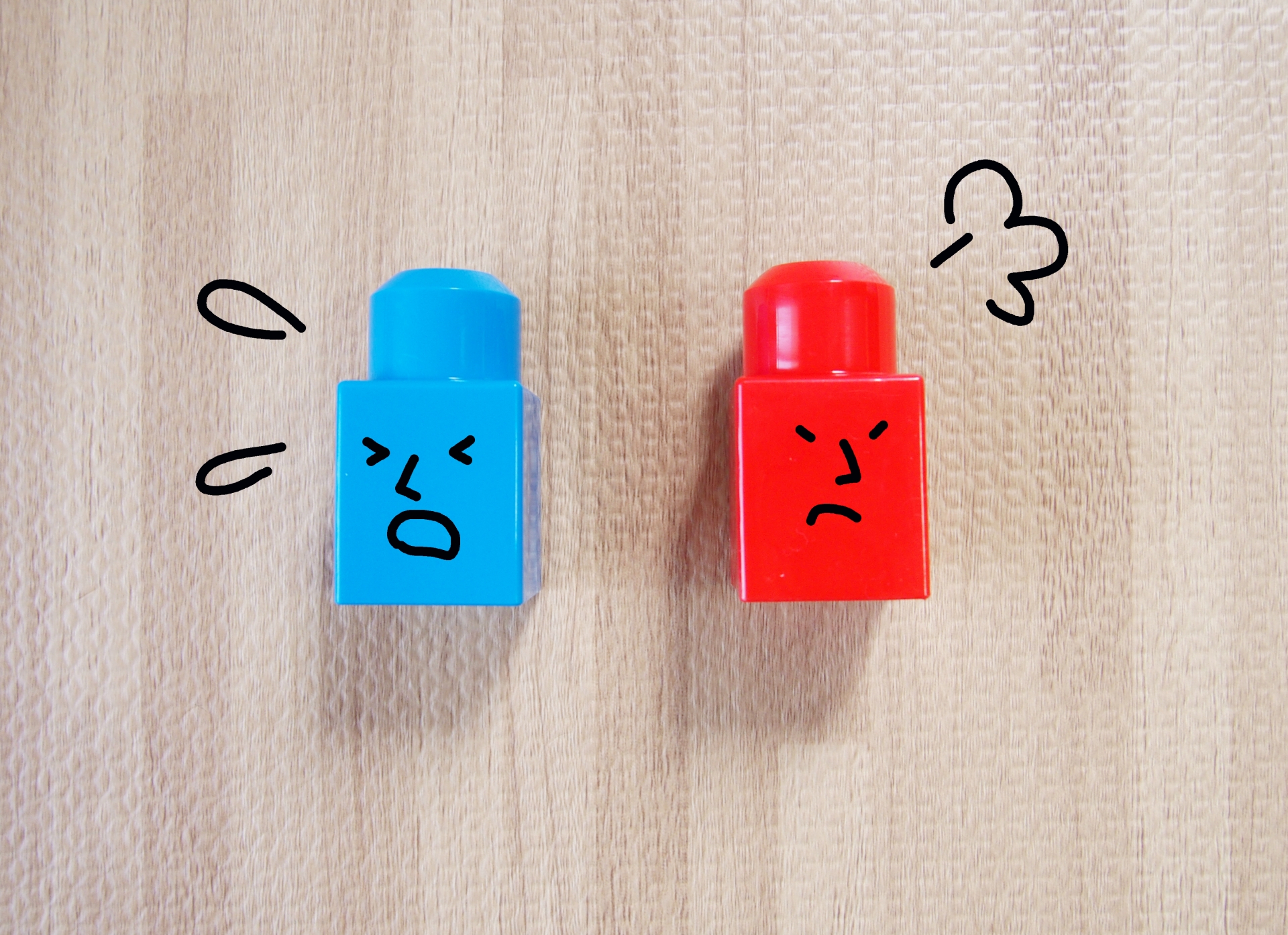子供の片付けはどのようにしつけをしたらいいのでしょうか?
いつまでたっても散らかしっぱなしのおもちゃを前に怒りながらお母さんが片付けてはいませんか。それ、間違った片付け方法です。子供に自分で片付けてもらうためのコツとポイントを紹介します。
前もって子供に遊ぶ時間を言っておくことや片付けやすくすることが大切です。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

2歳児の食事のしつけ方法!よくある悩みとしつけ成功のポイント
お子さんが2歳になり、食事のマナーやしつけに対してお悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。...
-

夜ご飯を食べない子供への対策!食べない原因とママにできる工夫
子供が夜ご飯を食べない事に頭を悩ませているママもいるのではないでしょうか。食事をしてくれないと栄養が...
子供が自分で片付けできるようになる時期
自分の子供は注意してもなかなかおもちゃを片付けてくれない。周りのお友達はきちんと片付けているのになぜうちの子は片付けてくれないんだろう。きちんとしつけしているつもりなのに。と悩むお母さんも多いでしょう。
実は子供のお片付けのしつけ方法は年齢やアイテム別で変わってきます。
一度確認してみてください。
【アイテム別】
- おもちゃ
小ぶりなものであれば歩けるようになってから遊び感覚で覚えてもらうのがいいでしょう。自分の意志で指定の場所に持っていくのが難しい場合にはお母さんが「ここに入れようね」と声をかけてあげても構いません。 - 絵本
こちらもおもちゃ同様に歩けるようになった頃から始めてみるのがいいかもしれません。子供にとって本と本の間に物ををしまうのは難しい作業です。
普段絵本を立てて収納している場合、はじめにお母さんが本の間に隙間を作って「ここに片付けてね」と手助けしてあげるといいですね。 - 衣服
始めは上着をハンガーにかけることからスタートしましょう。幼稚園などに入ると自分で服を畳んだりすることがあるので3歳前後から少しずつ練習していくと園での生活もスムーズでしょう。
【年齢別】
- 1~2歳
この時期は一人でやらせるのではなくお母さんと一緒に片付けに取り組むようにしましょう。
片付ける場所を家に見立てて、「お人形さんをお家で寝かせてあげようね」などおままごとの感覚で一緒に遊びながら片付けをするのがおすすめです。 - 3~4歳
この頃になると自分のことは自分で出来るという子供が増えてきます。
片付けを自分でできるようにするには子供がパッと見てこのおもちゃはここに片付ける。と分かるようにおもちゃ箱にイラストなどをつけてあげるのがポイントです。 - 5~6歳
この時期になると片付けないとという思いが合っても遊びたい気持ちが勝ってしまい片付けられない子供が多いです。
お母さんと競争しよう!などと言ってゲーム感覚で片付けに取り組んでもらうようにしましょう。そして片付けたらしっかり褒めてあげるのも大切です。
また次のおもちゃを出す際は出してあるものを片付けてから。とルールを決めたり、ご飯を食べる前に必ず片付けをするようにするなど決まった時間に片付ける週間を付けるとメリハリが付くでしょう。
子供の片付けのしつけでしてはいけない事
子供がなかなか片付けをしてくれない、反発をしてきてイラッとしてしまったときなどに1度は「なんで片付けないの!」と怒鳴ってしまったことありますよね。
分かっているお母さんも多いとは思いますが、片付けないからと言って叱ってはいけません。
叱るようになってから片付けられるようになった。でもそれはお母さんに叱られたくないからやっているに過ぎません。
うるさく言わない人がいなけれな片付ける気になるわけがなく、反発して余計にひどくなってしまいます。
そしてもう一つ、「片付けないなら捨てるよ!」と言ってしまうお母さんも多いでしょうが実は逆効果なのです。
子供が大切に遊んでいるおもちゃを言葉の通り本当に捨ててしまった人は居ないでしょう。捨てられないと分かった子供は「捨てるよ」と言われても本当に捨てるわけじゃないから大丈夫と学習してしまいます。
片付けのしつけに役立つ魔法のコトバ
「片付けておきなさい」「そのくらい自分で出来るでしょ」
やってほしい一心で何も考えずに発してしまっていることもあるでしょう。
ですが子供にとってはハードルが高い言葉なのです。
子供に一言言ってしまいそうと思った時は「一緒に」という言葉を思い出してください。
「お母さんと一緒に片付けようね」「後でお母さんと一緒にやろうね」という言葉のかけ方ひとつでお子さんは安心します。
そして子供の心を動かす魔法の言葉がもう一つあります
子供が片付けやすい部屋の作り方
片付けをスムーズにしてくれるためには声掛けだけでなく部屋づくりも重要になってきます。
靴をきちんと揃えてくれるようにするための魔法の仕掛けを例にして見ていきましょう。
まずは子供の靴を置いておく定位置を決め、チョークで靴の形の絵を描きます。
(チョークで書くことに抵抗がある場合にはテープを目印に貼るなどでも大丈夫です)
すると、いつの間にか揃えて置いてくれるようになるのです。
小さな子供にはひと目で分かる仕掛けのほうが言葉よりも効果的なようです。
このような仕掛けを考えるときのコツとして
- 片付けるための動線と動作はシンプルに
- 頻繁に使うものの定位置は取り出しやすいところに
- 一緒に使うものは同じところにしまう
- いつも同じ場所で管理
の4つのコツを意識して片付けやすい部屋づくりの参考にしてください。
子供をしつけるというよりも習慣化させる事が大切
子供をしつけするという考え方より、自分から片付けてくれるような習慣付けをしてあげることが大切になってきます。
片付けの時間を決める
遊び始める前から片付ける時間を決めて子供に伝えておくと、そろそろ片付ける時間だ。と心構えできますよね。この時に時間がきても片付けを始めない子供も居るかと思いますが、その場合の対応で注意したい事が2つあり、1つ目は片付けの時間を変更することです。これは子供がすぐに片付けなくても良いのかと勘違いしてしまう為です。そしてもう1つは親がおもちゃを片付けてしまうことです。子供が自分で遊んだおもちゃは自分で片付けるという習慣がつくように出来るだけ親は手を出さないようにしましょう。
遊び感覚でお片付け
片付ける習慣が付かない時は、ゲーム感覚で「どちらがおもちゃを先に片付けられるか競争しよう」と勝負してみたり、「このおもちゃのお家を教えて」と子供に教えてもらうような声掛けをしてあげると得意げに片付けをしてくれるかもしれません。
表を作る
片付けが出来たらシールを貼ったりスタンプを押したりするようにすると、片付けが楽しくなり率先して片付けてくれるようになる子供も多いです。
好きなキャラクターのシールなどを使うと達成感や喜びが味わえて子供の自身もつきます。