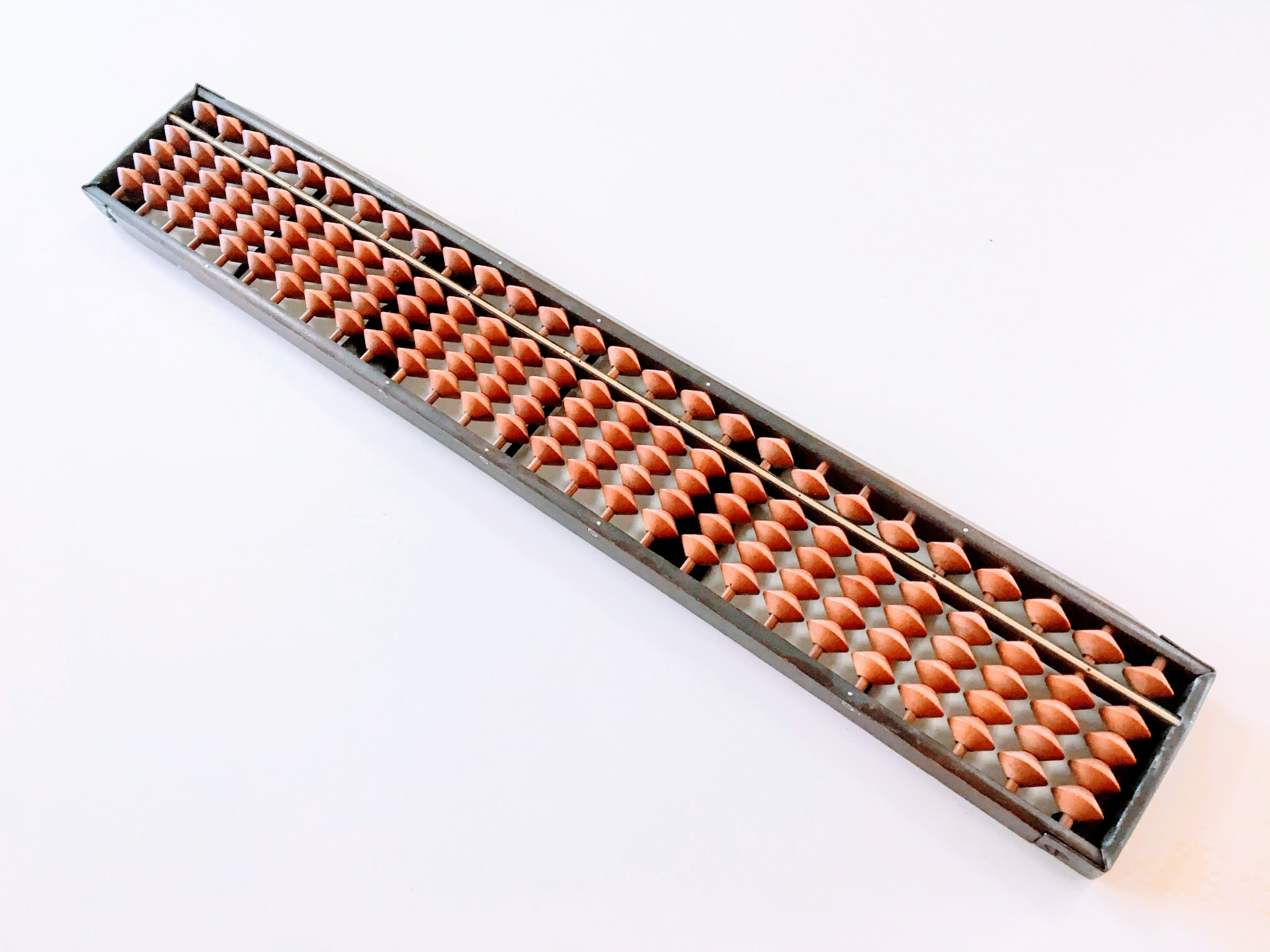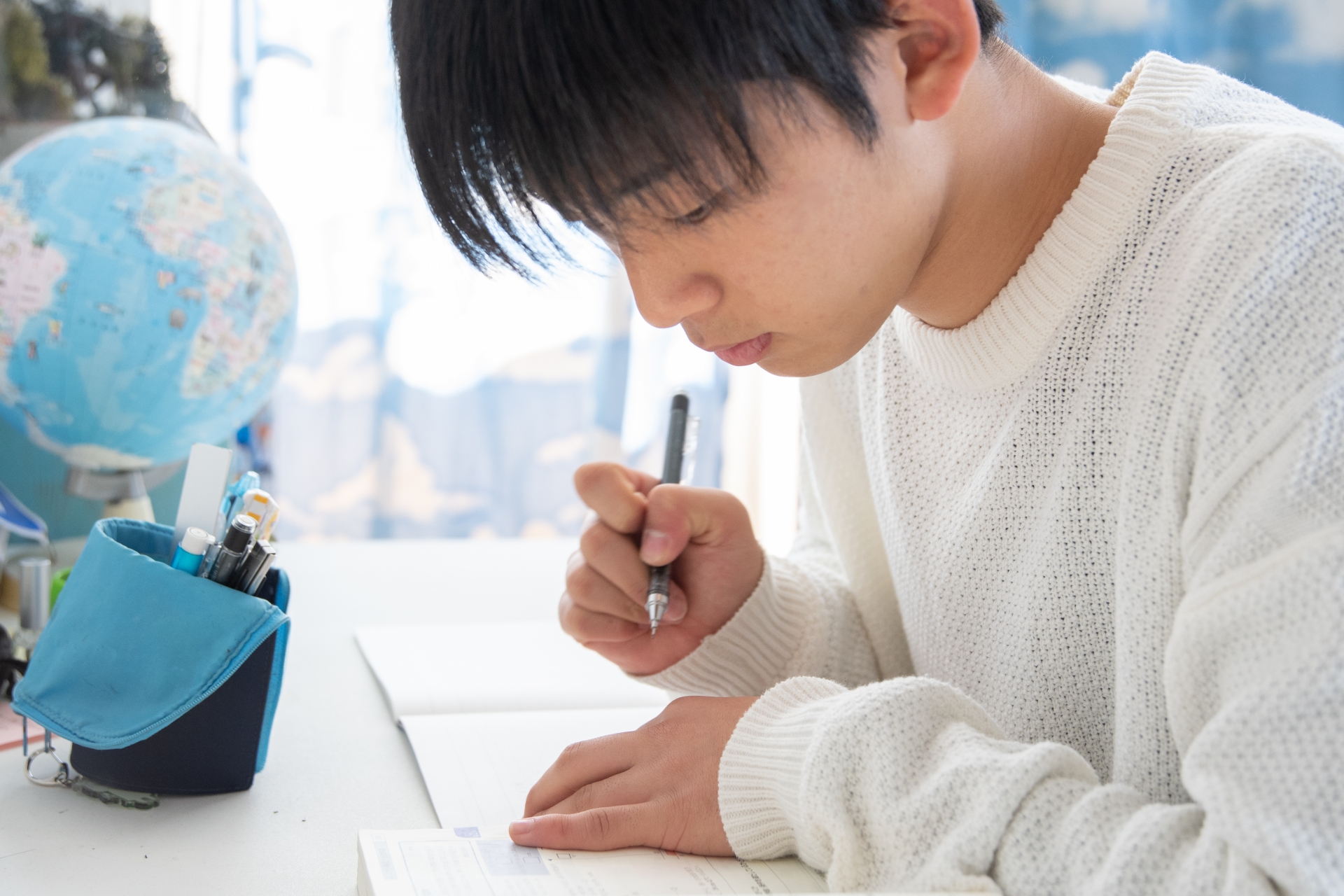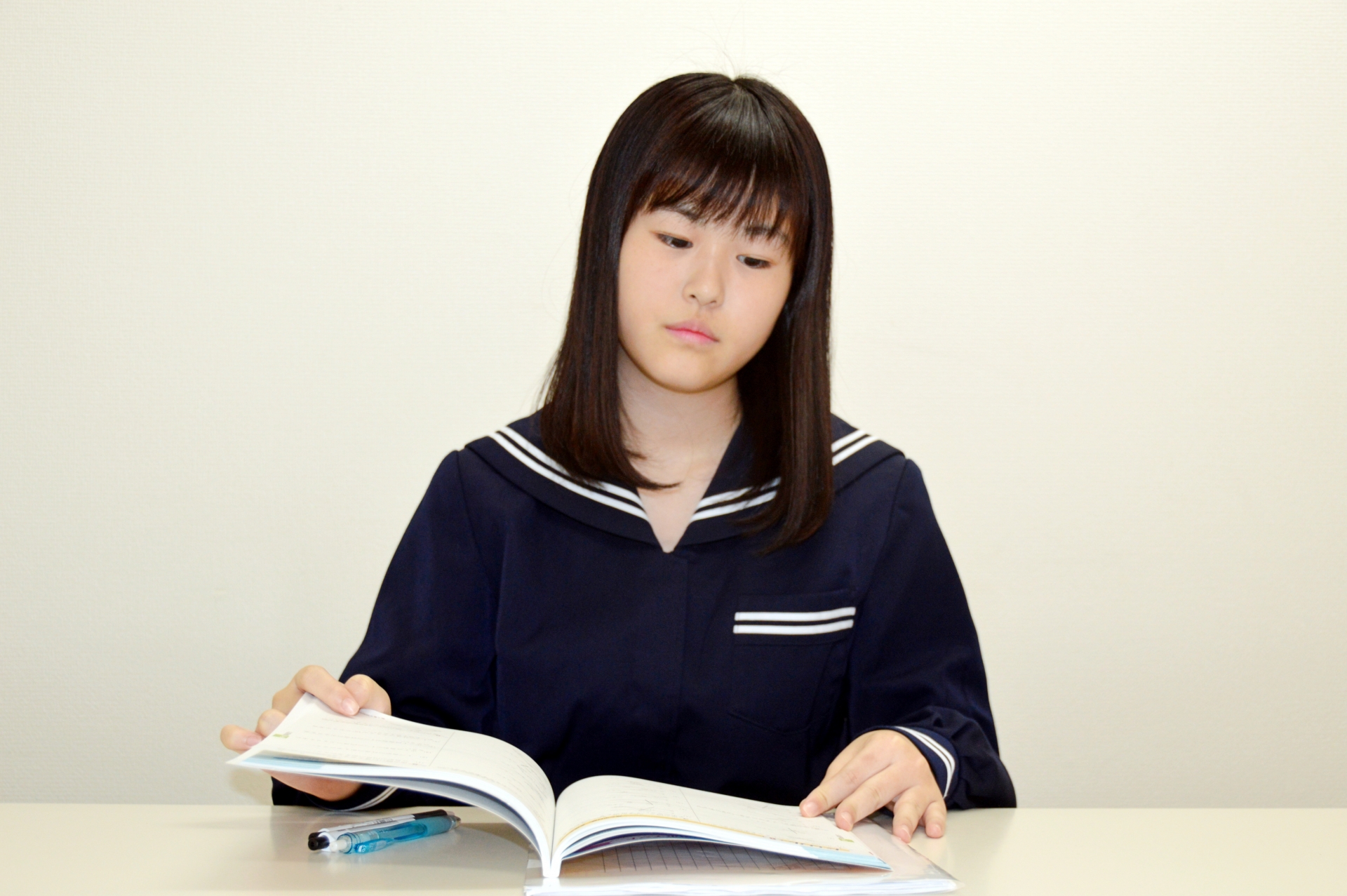小学生の習い事は必要なのでしょうか。習い事を始めるときには、役に立つのかや続けることができるのかなどどんなメリットがあるかで決めたくなります。
子供が習い事をしたいと言っているのであれば、一度体験してみるのもいいでしょう。
家庭によって、送り迎えができない、他にも習い事をしているため時間的にも厳しいなど理由があるときには子供と一緒にどうしたらいいのかを考えるのもおすすめです。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

反抗期の息子の特徴と接し方について。反抗期に疲れた親の対処法
子供が反抗期を迎えると、今までの素直な息子とは別人になってしまい、戸惑ってしまう方も多いと思います。...
-
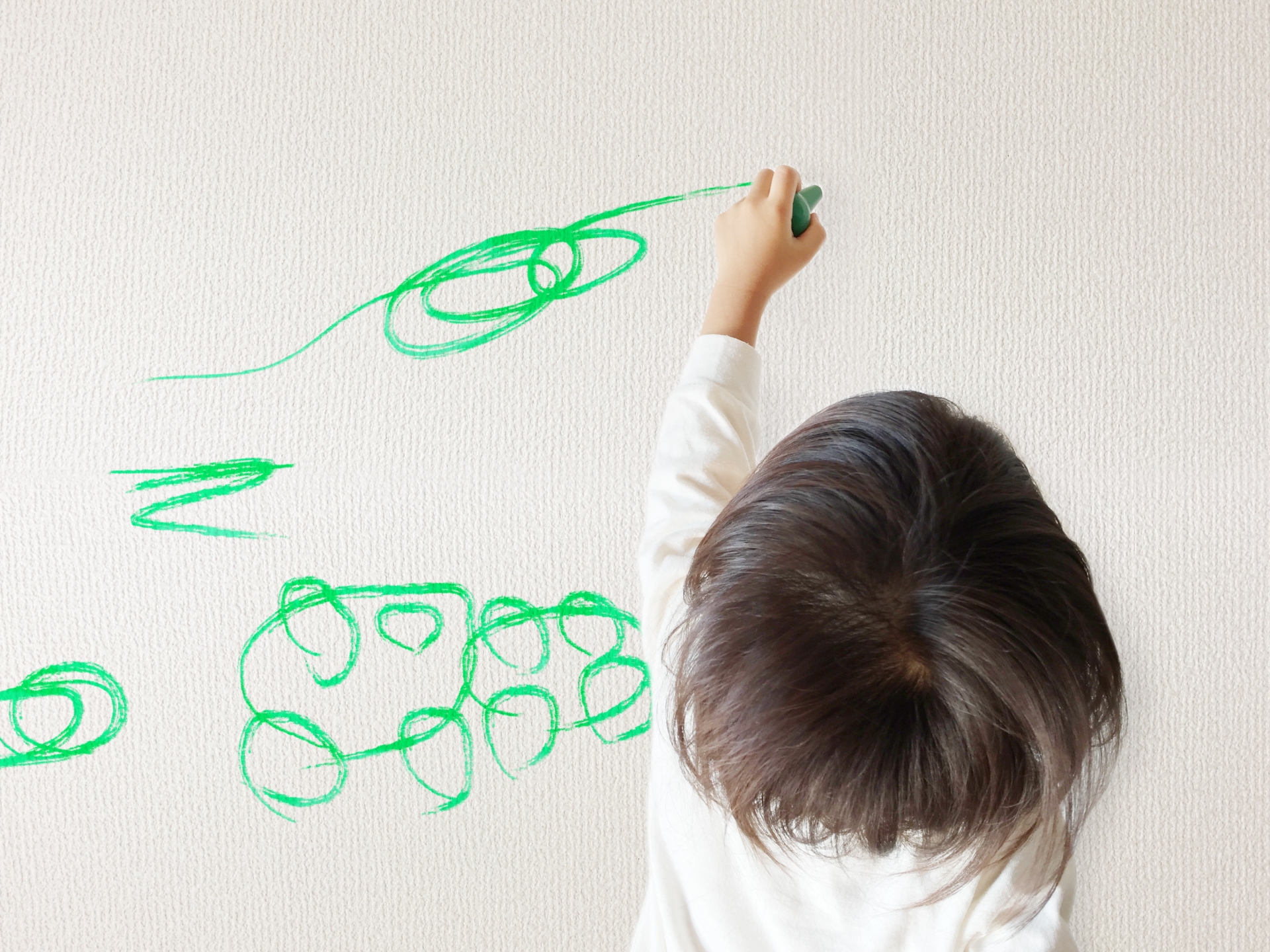
6歳の反抗期【中間反抗期】女の子の気持ちの様子と特徴・接し方
6歳の女の子の子育てをしているママの中には、子供の反抗的な態度に頭を悩ませている人もいるのではないで...
-
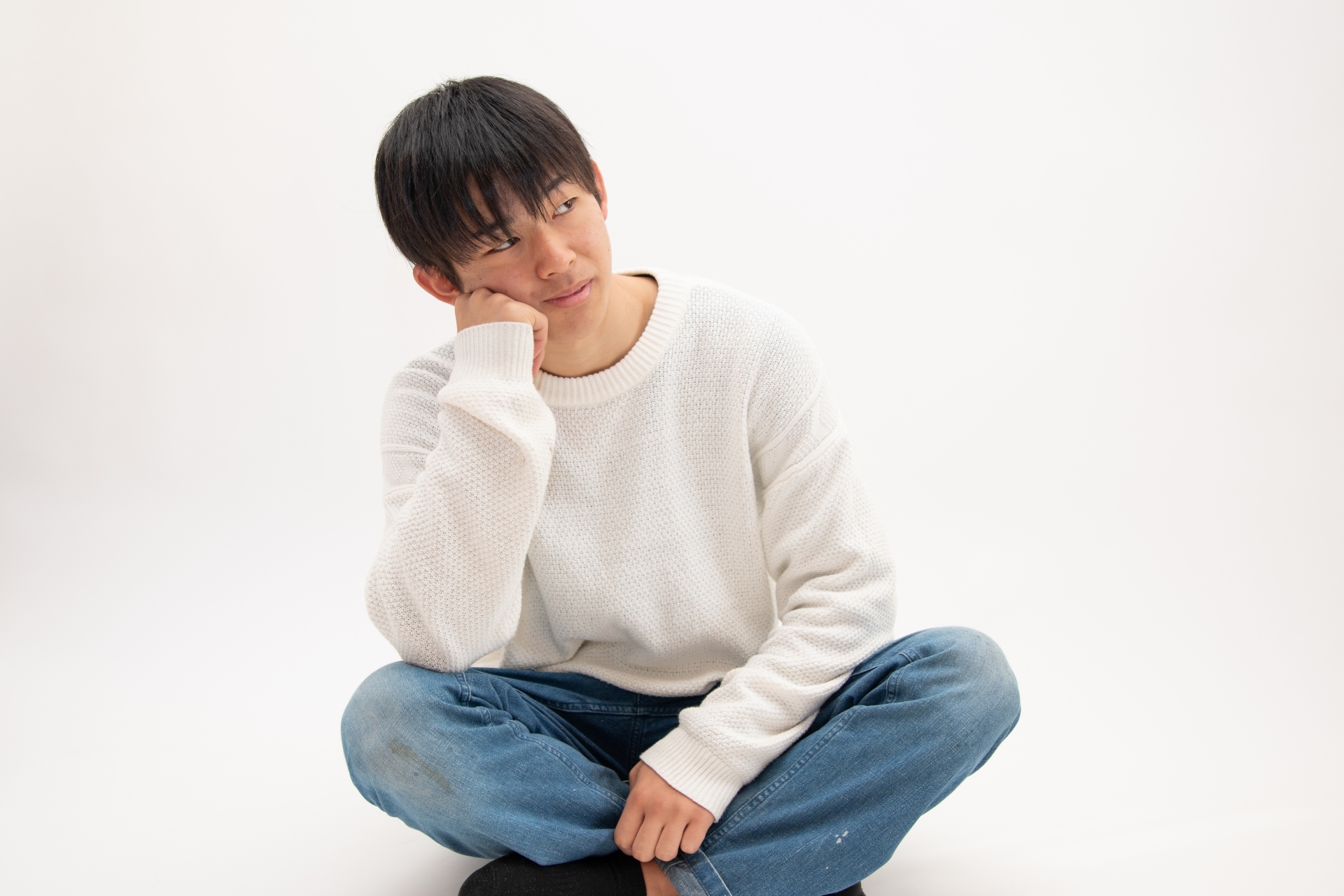
息子の反抗期と父親の役割、子供扱いせず求められるまで見守ろう
反抗期を迎えた息子の対応に戸惑う母親は多いですが、反抗期の息子と父親との関係に悩むこともあります。...
小学生に習い事をさせるのは必要?多ければいいということではありません
子供が小学生ともなると、周囲にも子供に習い事をさせているご家庭が増えてくるものです。ですが、必ずしも習い事をさせる必要があるかと言われれば、それは一概にそうとは言えないかと思います。
小学生に習い事をさせるかどうかはその子次第
子供自身の自主性にまかせて習い事を増やすのであれば、それはそれで子供のためにもなるかもしれませんが、子供にとって必要だからと、親が次々と習い事を増やしてしまうのでは、子供にとってはいつまでたっても「やらされてる感」が消えない原因となることも。
小学生の習い事が必要かどうかの判断基準
周りの子供たちがみんな何らかの習い事をしているからといって、我が子にも何か習い事をさせたいと思う必要はないでしょう。小学生に習い事をさせるかどうかは、家庭の事情もありますし、何よりもその子が興味を示さないことであれば、無理にでも習わせることがプラスに働くことは少ないかもしれません。
習い事はやりたいことを伸ばしてあげるきっかけとなるべき
しかし、彼女が書道を続けていたのは、あくまでも自分の意志であり、親や周囲の人から無理やりやらされていたわけではありません。親にとっては子供の将来を思って始めさせた習い事も、まだ小学生の子供にとっては、遊ぶ時間が削られるだけの、マイナスな事だとしか感じないのであれば、それはその子にとって有意義な時間とはけっして言えないでしょう。
金銭面なども考慮を
習い事をするということは、家計から費用を捻出することになります。長続きするかどうかはやってみなければわかりませんが、いくら子供がやりたいことでも、続けることで家計を圧迫したり、親の送り迎えなどの負担も増える可能性がありますので、実際に習い事を始める前にリサーチをしておく必要はあります。
小学生に習い事のメリットについて
習い事で自分に自信をつけさせる
どんな習い事もその子によってペースは違えど、続けることで少しずつ上達していきます。はじめはできなかったことも、習い事を続けるうちにできるようになることで、自分自身に自信が持てるようになります。
子供の世界を広げられる
習い事を通じて知らないことを学んだり、学校以外の友達との出会いを通じて、人との付き合い方や社会への興味を引き出すことができます。
運動系の習い事なら思う存分体を動かせる
体育の授業や帰宅後の外遊びだけでは、十分に体を動かす機会が少なく、子供もストレスが溜まってしまうものです。運動に関する習い事を通じて、体を動かす機会を増やすことで、精神面でも安定するといった効果も期待できるでしょう。
デメリットにはどんなものが?小学生の習い事
小学生の習い事は、平均すると週に2回から3回ほどのようですが、スポーツに関する習い事のように、中にはほぼ毎日のように練習があるケースもあります。本当に自分が強くなりたい、人よりも早く上達したいと思っているのであれば、習い事にかける時間が多くても問題ないかもしれませんが、やはり習い事が多すぎることで生じる弊害もあるようです。
習い事を増やすと起こりやすいこと
さらに小学生くらいの小さい時期は、親の送迎が必要になるケースも多く、兄弟が別々の習い事をしていたりすると、家族の食事や就寝時間にも影響が出ることも珍しくはありません。
もちろん、習い事を続けることで出費もかさむため、他のことで我慢を強いることにもなりかねないのです。
小学生の習い事は子供がやりたいと思うなら必要
動機を探る
まだ小学生くらいの頃だと、仲の良いお友達がやっている習い事を、一緒にやりたいと言いだすこともあります。しかしそれが、本当に自分がやってみたいと思っていることであれば、親としても前向きに検討してあげたいと思うものですが、単なる思いつきだったり、お友達との遊びの延長でやりたいと言っている可能性もありますので、まずはどうしてその習い事を始めたいのかを、具体的に聞いてみる必要があるでしょう。
実際に体験させてみる
小学生向けの習い事の多くは、実際に始めてみる前に無料体験を実施していることが多いため、まずはそちらを利用してみるという方法もあります。