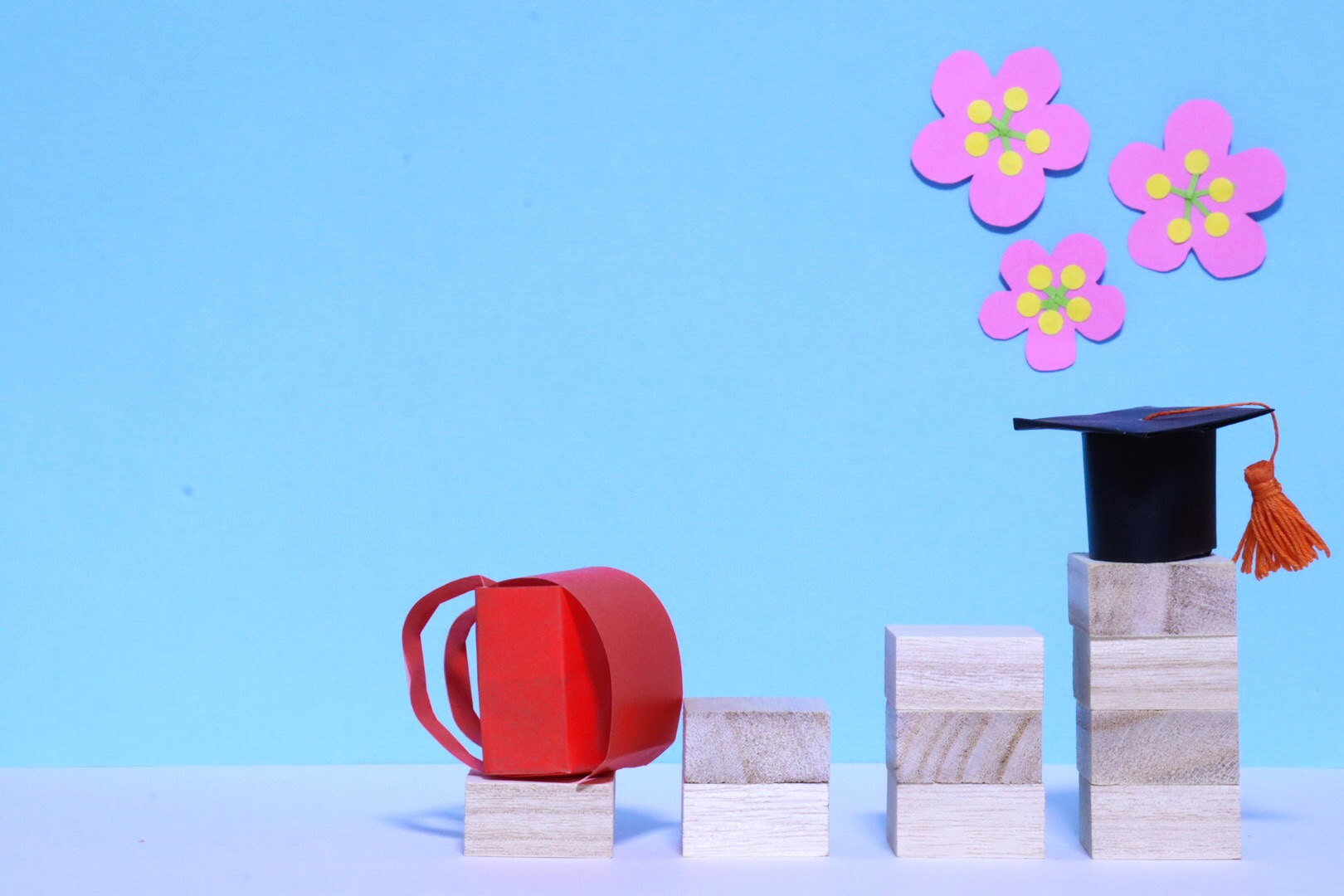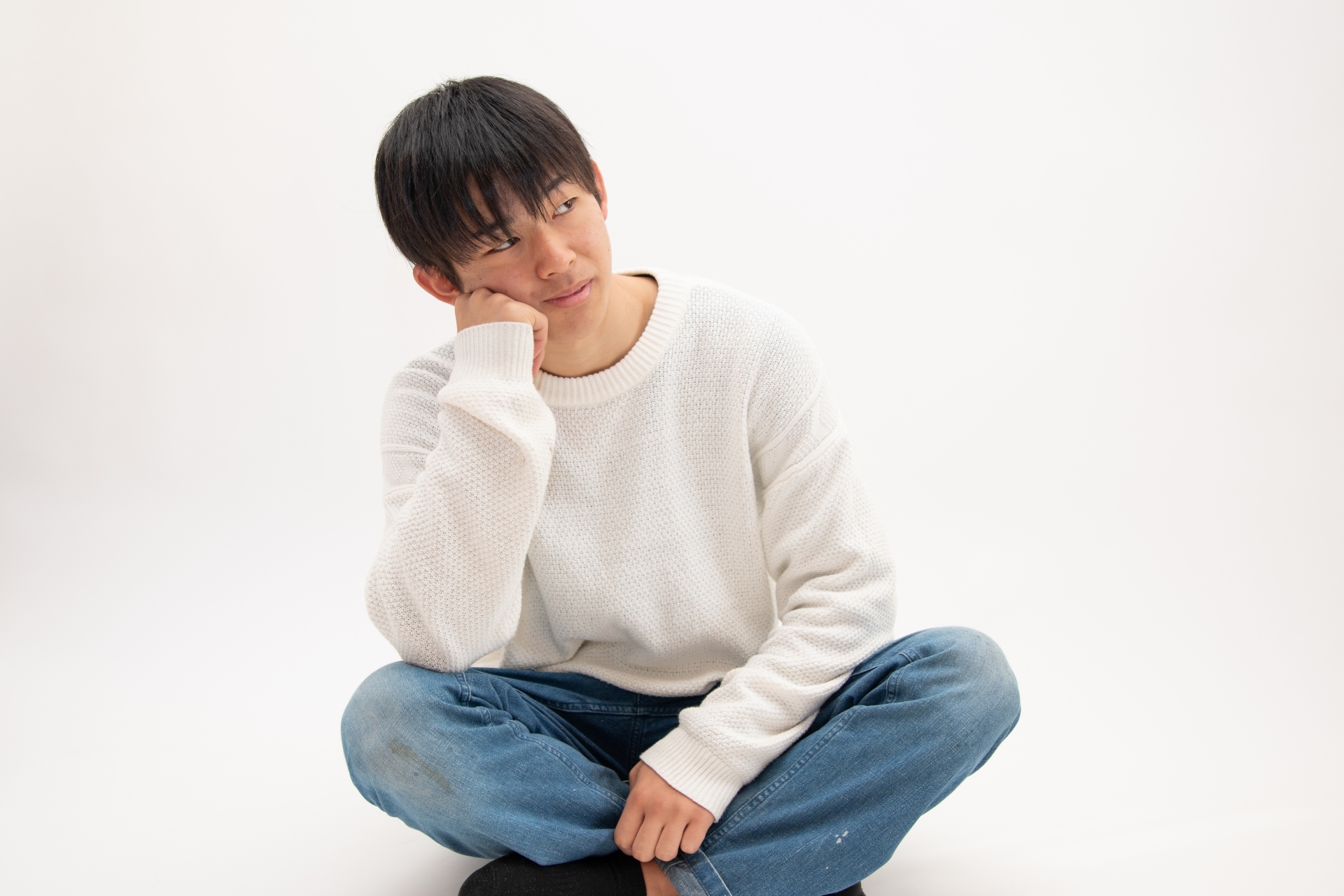お店や公園・家の中で突然子供が叫ぶと、親もびっくりしてしまうものです。子供が突然叫ぶのは一体どんな心理が働くからなのか、子供の気持ちを理解したいと考えているママもいるのではないでしょうか。
ここでは、2歳の子供が叫ぶ時の心理についてお伝えします。子供の気持ちを知ることで、状況に合った対処が出来るようにしましょう。
また、親がしてはNGなことや日頃から心がけたいことについてもご紹介します。こちらも是非参考にしてみてください。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
2歳の子供が叫ぶ心理・叫ぶ時の心の中
2歳ごろになるとイヤイヤ期がやってきます。
このイヤイヤ期と叫ぶ心理は実は関わりがあります。
2歳になると徐々に物事を理解し始めており、大人の言うことなどもわかってきます。
- ある程度2歳の子は自己主張が強くなるのですが、なかなか自分で出来ない事も多く、その葛藤から叫び声や奇声をあげてしまうようです。自分の思いをうまく言葉にできなかったり表現できなかったりする場合にもどかしい気持ちが声に出るのでしょう。
- また、自分の思うように体が動かなかったり自分の思い通りにならない事があると叫び声や奇声をあげて主張をします。
- また、まだわからないことだらけのことばかりなので、思いがけない出来事に遭遇するとストレスがたまって声に繋がる場合もあります。
イヤイヤ期の子供が叫ぶ心理を知って対処を!怒るのはNG
イヤイヤ期の子どもが叫んだり奇声を上げたりすると、どうしてそんな声を出すのかとつい叱ってしまいたくなります。
周りに人がいると余計恥かしくてやめてほしいと思うでしょう。
しかし、ただ感情にまかして叱るだけでは子供がさらに不安定になってしまいます。
イヤイヤ期の子どもを注意する場合は怒るのではなく上手に叱られるようになりましょう。
子どもが叫んだ場合は、なぜ叫んでしまったのかをよく観察し、親が諭すようにしましょう。
きっとうまくいかない事に対するいら立ちがあって叫んだ場合もあります。
叱ってしつけをするよりもほめて伸ばしてあげるほうが子どもの脳にも健康で、効果的です。
怒って自分の感情をぶつけるのではなく、子どもに寄り添って成長を手助けしてあげるようにしましょう。
子供が叫ぶ心理・子供の癇癪について
子どもが叫ぶ心理としては、子どもの癇癪が原因の場合があります。
子どもが癇癪を起こすとはどういった事を表すのでしょうか。
原因は様々ですが、叫んだり泣きわめいたり、全身を使って暴れるなどして嫌な気持ちを表現したりします。
場合によっては、自分の体を傷つけたり物を投げたり、人の事を叩いたりする場合もあります。
癇癪が原因で、子どもが叫び声をあげている場合もある
何かうまくいかなかったり不愉快なことがあると癇癪を起こす子どもは多いものです。
癇癪を起されるのは親としては困ることですが、そのことでイライラしたり子どもを怒るのは我慢しましょう。
子どもが癇癪を起さないように、日々の生活で子どもとのコミュニケーションの方法を見直すようにしましょう。
子供が叫ぶときの行動を見て冷静に!こんな時はしっかり対処を
子どもが叫んだり奇声をあげた場合は、何が原因なのかしっかり子どもの様子をみて見定めてあげることが大切です。
そのうえでなきやまない場合は、様子を見るのも大切です。
子どもが癇癪を起しているとどうにか気持ちに応えてあげたいと思うかもしれません。
しかし、だめなものはだめだという態度は曲げずに、毅然とした態度をとることも大切なのです。
子供は親の影響を受ける・親の態度や行動を見直そう
子どもが癇癪を起すのは、子どもの性格でもあり個性です。
しかし、ただ個性だからと放っておくのは違います。
子どもはなぜ癇癪を起すのか、しっかり寄り添ってあげる必要性もあるでしょう。
そして、子供は大人の行動もよく見ています。
一番近くにいる大人はやはり、親なので親の性格や行動も子どもの行動に大きな影響を与えるでしょう。
親の心に余裕がなく、いつも怒っている親だと、子どもも怒りっぽかったり不安定になりがちになってしまいます。
そのため、子どもの癇癪や叫び声をどうにかしたい場合は、まずは親の日ごろの行動や子どもに対する態度を見直す必要があるでしょう。
子どもがのびのびと毎日を暮らせるように、親にも心の余裕がなくてはなりません。
そして、子どもが何を主張しているのかを、子どもの心に寄り添ってあげてみてくださいね。