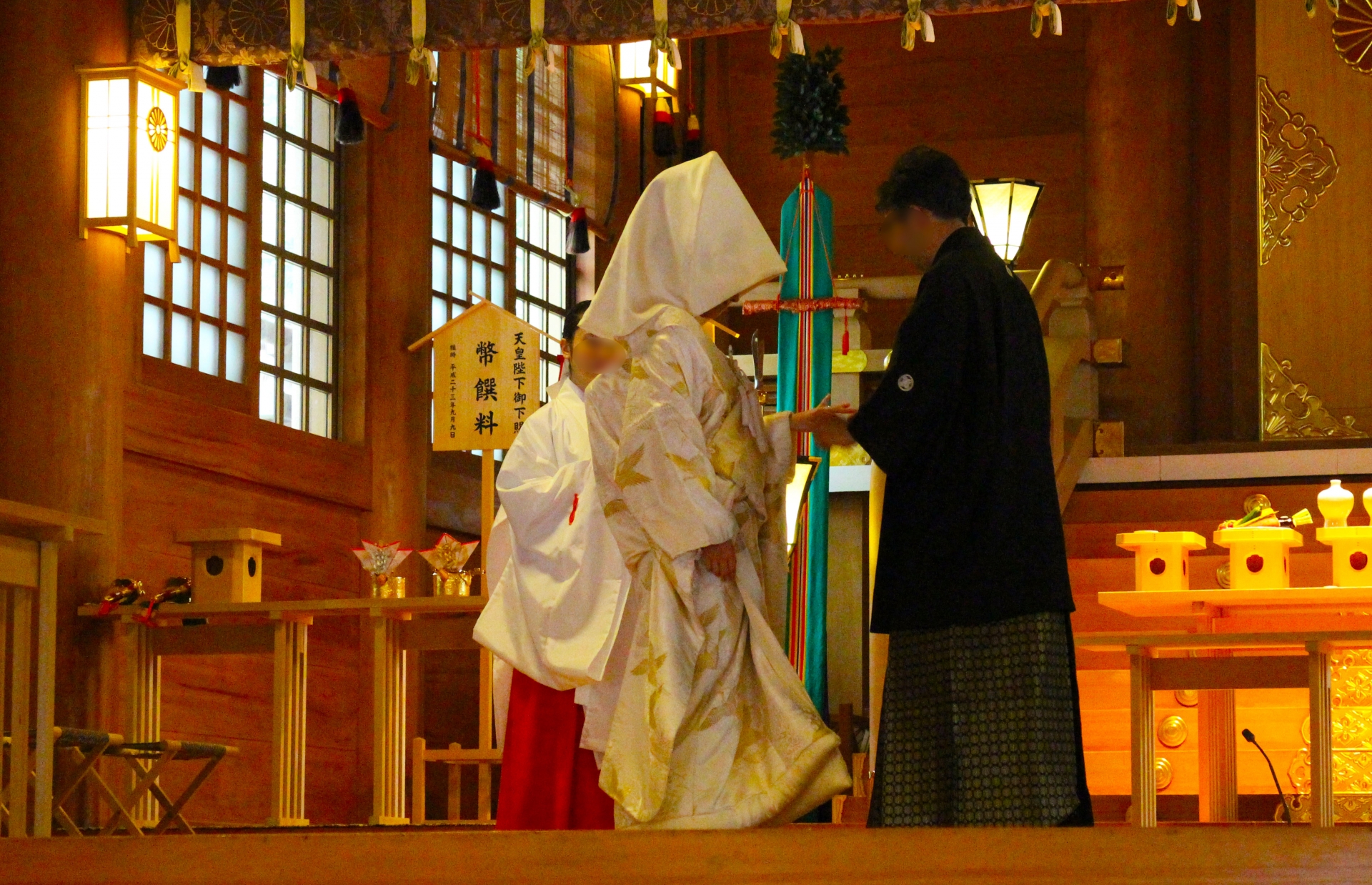赤ちゃんの食事のしつけはいつから始めたらいいのでしょうか。
できるだけ早いほうがいいのでしょうか?それとも、スプーンを上手に掴めるようになってから?
赤ちゃんの食事のしつけは、残さずに食べるや汚さずに食べるということではなく自分で食べることを目標にしてみましょう。食べることができたら褒めてあげてください。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

プールに赤ちゃんを入れるならいつからがベスト?目安となる月齢
プールに赤ちゃんを入れたいけど、いったいいつから入れるの?今回はこの疑問についてお応えしたいと思いま...
-

6ヶ月の冬の服装選びのポイント!赤ちゃんも快適でママも楽しい
生後6ヶ月の赤ちゃんがこれから冬を迎えるとき服装の選び方が気になるところ。寒い冬でも赤ちゃんが快...
-

【二人目出産】上の子は入院中どこで誰に見てもらうのが良いのか
すでに子供がいて、二人目の出産を控えている妊婦さんにとって、一番の心配事は、出産のことよりも二人目出...
-

【生後6ヶ月の赤ちゃん】よく寝る子の特徴と寝ない子への対処法
赤ちゃんの睡眠時間には個人差があり、よく寝る子もいれば沢山泣いてママを困らせてしまう子もいます。...
-

1歳10ヶ月の子どもの睡眠時間の目安と子どもに合わせた就寝時間
赤ちゃんや子どもの月齢によって、それぞれ理想の睡眠時間や生活リズムがありますが、子どもの体力や性格に...
-

1歳がたくさん寝る大切さ。時間を決めた生活は将来にも影響する
1歳は表情や行動も豊かになり、ますます可愛さを感じる年齢です。しかし、毎日一緒にいるママにと...
-

生後7ヶ月の赤ちゃんの睡眠時間、生活リズムの作り方と入眠儀式
これまで不規則に起きたり、数時間おきの授乳が欠かせなかった赤ちゃんも、生後7ヶ月になると生活リズムが...
-

乳児の冬時期の布団選びや注意点、防寒対策+事故防止を意識して
冬の寒い時期に乳児を寝かせる時、寒くないだろうか、汗はかいてないかかとママは不安になってしまいます。...
いつから赤ちゃんの食事のしつけを始める?まずは食べることを優先
まずは細かいマナーにこだわらず「食べる」ことを優先して、しっかりと食事の量を食べられる身体作りを目指しましょう。
但し、食事中は座るものだということは身体で覚えさせておくと後々の躾が楽になります。
食事の時間は赤ちゃんが脱出できないような椅子に座らせるようにしましょう。
自分でスプーンやフォークを使えるようになるまでは親が食べさせてあげるか、自分で手づかみで食べさせます。手づかみで意欲的に食べさせる事は大切ですが、食事はカトラリーを使用して食べるものである事も知らせておく必要があります。
スープやライス等手づかみできない料理は親がスプーン等を使用して口に入れて与えると、子供は食事をする際にはスプーン等を使用するものであるという事を理解します。
食事は身体を作る大切なエネルギー源です。赤ちゃんの小さい身体がどんどん大きくなるために良質の栄養が摂られるように、とにかくもりもり食べるようになることが大切です。
マナーにこだわって指導するあまり赤ちゃんが食べることが嫌いになってしまわないように気をつけましょう。
しかし、食事は1日3回生きている限り食べ続けるものです。
赤ちゃんに食事のしつけをするときのポイント
赤ちゃんに食事の時間を意識させて「今は食べる時間である」ということをしっかりと理解させることが大切です。
そのためには、食事の準備をしてあかちゃんに「これから食事の時間が始まる」ということを知らせます。赤ちゃんにエプロンを見せて「さあごはんを食べますよ。エプロンをつけようね」などと声かけをしてエプロンをつけます。食事に必要なスプーンやフォークなどのカトラリーを並べ、食事を置いたら「いただきます」と言います。
親が毎回「いただきます」と言っていると赤ちゃんもまねをして言うようになります。
食事の時間はとにかく立たせないようにしましょう。赤ちゃんが脱出できないようなテーブル付きの椅子に座らせたりして、食事中は立たせないようにしましょう。
赤ちゃんの食事のしつけは押し付けないことが大切
赤ちゃんのうちは遊び食べをするのが当たり前です。
大抵の赤ちゃんはするでしょう。
初めて出た食べ物などはどんな物なのか確認するためにも手で触って撫で回したりテーブルにぶつけてみたりと大人から見ると「行儀の悪い行為」をします。しかし、目くじらを立てて注意すると赤ちゃんは食べる意欲を失ってしまいます。「食べ物を確認しながら食べているのだ」と大らかに見守りましょう。
食べ物をポンと投げるのは、もういらないか、投げる事を楽しんでいるのでしょう。
投げて飛んでいく様子が面白いのは分からなくもありません。そんなときも「こら!投げたら駄目だよ!」と叱らずに「食べ物は投げてはいけませんよ」と普通の声で言い聞かせて教えましょう。
また、怒らなくても「あらら!いや~食べ物投げないの!」など高い声で対応していると母が喜んでいると勘違いしてもっとやる場合があります。低めの声で冷静に「投げないんだよ」と言葉少なく言うなど遊んでいる雰囲気が出ないように気をつけましょう。
ついうち気になってしまう赤ちゃんの食事正しいサポートの方法
折角用意した食事は全て食べてほしいと思いますが、食べさせてばかりいると自分で食べる意欲が減退していきます。赤ちゃんのうちは食事を自分でするのは大変な労力が必要です。親が常に口に入れてくれていると、赤ちゃんはそれに慣れて食事は食べさせてもらえるものと思ってしまいます。そうなると大変です。親はそのうち自分で食べるようになるだろうと考えていてもその日はなかなかやってきません。
「自分で食べなさい」と毎日言っていますがさっぱり改善されません。
自分でもりもり食べる赤ちゃんは食事を出すだけでよいのですが、我が家の子供のように食事に対する関心が薄いタイプの赤ちゃんは注意が必要です。親がずっと食べさせていると大きくなっても自分で食べなくなってしまうので、とにかく自分で食べるように仕向けることが大切です。
周囲のお母さんの話を聞いていると、自分で食べない場合には思い切って食事を下げてしまうという強硬手段が有効なようです。「今食べないと本当に下げられる」という体験をさせると自分で食べるようになります。
ただ、一口食べさせると美味しいと気に入って自分で食べるようになるようになる場合もあります。料理の味を知らせるためにまずは一口食べさせてみるのもよいでしょう。
赤ちゃんが食事に慣れてきたら始めたいしつけ
食事の前と後のあいさつは食事を与え始めた時から親だけでも言うようにします。赤ちゃんが食事に慣れてきたら一緒に言うように促していきましょう。
最も大切なのが食事が始まったら終わるまでは立たせないことです。
「まだあかちゃんだから…」と大目に見ていたらそれが続き、食事中着席させるようにしつけるタイミングがなくなります。ある時から突然着席するように指導しても子供は「昨日まではよかったのにどうして急にだめなの?」と理解できないでしょう。それに習慣と言うのはなかなか変えられないものです。赤ちゃんのうちから着席して食べる習慣をつけさせましょう。足が宙に浮くような椅子に座って足をブラブラさせないようにするのも同じです。言っても聞かない赤ちゃんのうちは足がブラブラできない椅子に座らせるとよいでしょう。