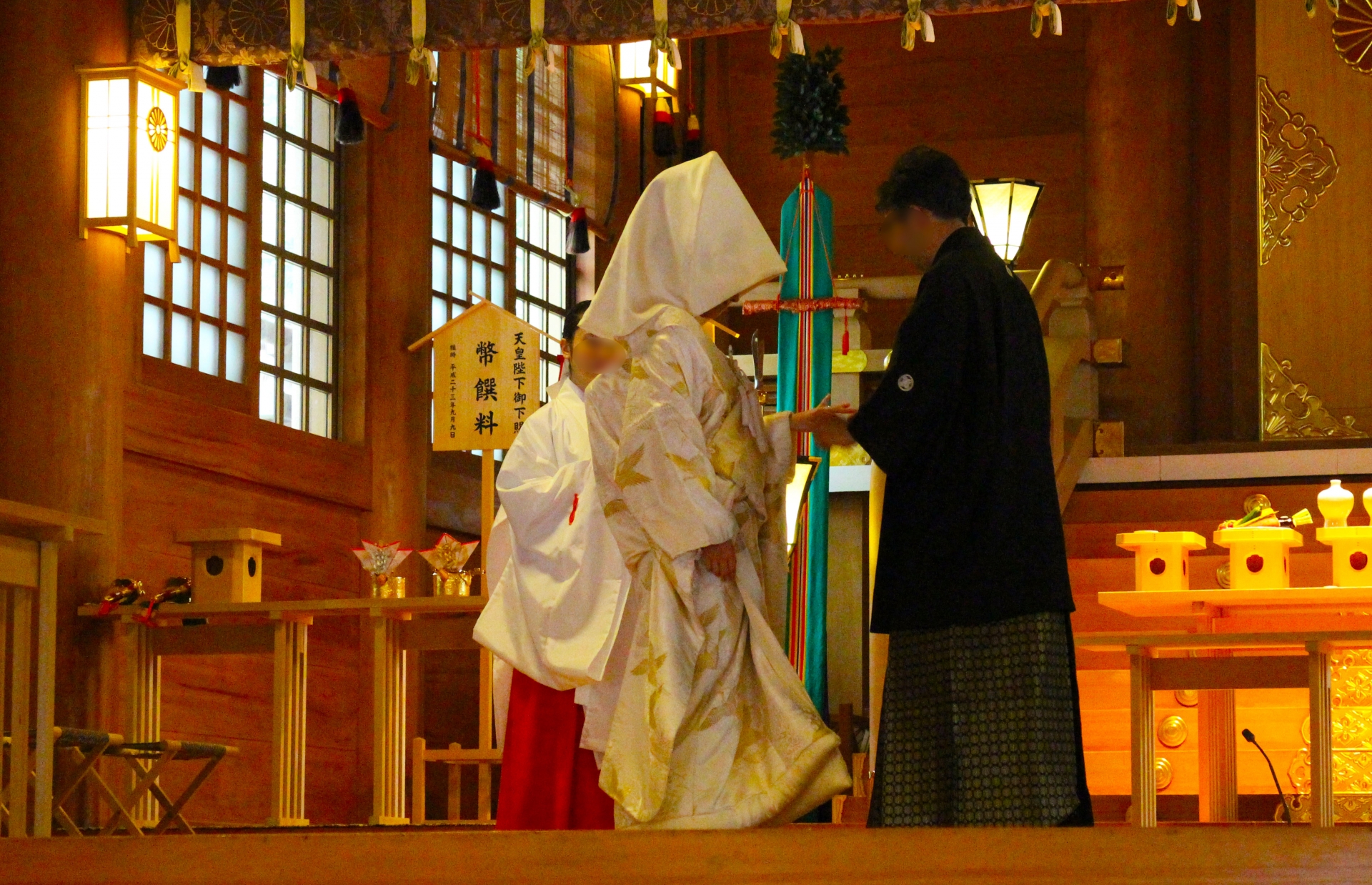生後2ヶ月の赤ちゃんは、まだまだ睡眠時間が安定しないので、睡眠リズムが上手く作れずに子育て中のママを悩ませることが多いのではないかと思います。
ここでは、生後2ヶ月の赤ちゃんを育てているママのために、生後2ヶ月の赤ちゃんの平均的な睡眠時間や、平均よりも睡眠が短い時、長い時の注意点、安定した睡眠リズムを作るためのポイントなどについて紹介していきます。
子育てで忙しいママ自身のケアについても解説しますので、ぜひ最後までご覧になって子育ての参考にして下さい。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

4ヶ月になると赤ちゃんはママに睡眠時間をプレゼントしてくれる
赤ちゃんはまさに天使です。そこにいてくれるだけで、周りのみんなを癒し笑顔にしてくれます。...
-

2才の子どもが夜中に起きる・夜泣きをするのはなぜ?原因と対策
2才の子どもを育てているママの中には、子どもが夜中に起きるようになる・夜泣きが再び始まってしまったこ...
-

2歳児のお昼寝時間の目安・寝かしつけのコツや寝ない時の対処法
一般的には生後6ヶ月を過ぎた頃から体内時計が整い睡眠リズムが出来てくると言われていますが、睡眠の環境...
-

1歳がたくさん寝る大切さ。時間を決めた生活は将来にも影響する
1歳は表情や行動も豊かになり、ますます可愛さを感じる年齢です。しかし、毎日一緒にいるママにと...
-

妊娠中の上の子の抱っこ事情!赤ちゃん返りも上手に乗り切るコツ
妊娠中の上の子の抱っこについて悩むお母さんもいるでしょう。抱っこはいつまでしてもいいのか、抱っこ...
-

生後3ヶ月の赤ちゃんの就寝時間と生活リズムの作り方のポイント
1日のほとんどを寝て過ごしていた赤ちゃんも、生後3ヶ月頃から昼夜の区別がつくようになり、夜にまとめて...
-

生後3ヶ月の服装【秋の選び方】赤ちゃんのためのポイントを紹介
生後3ヶ月の赤ちゃんの服装は秋になるとどんな着せ方をしたらいいのか悩みませんか?気温が下がる秋は...
-

3ヶ月の赤ちゃんの睡眠時間と寝ないときの対策・心がけたいこと
3ヶ月頃の赤ちゃんは、新生児の頃に比べるとまとめて寝てくれる時間が長くなります。ですが、まだ大人と同...
生後2ヶ月の赤ちゃんの睡眠時間の平均とリズム
起きている時間はたったの6時間程度なので、まだ一日の4分の3は寝ていることになります。
それでも生まれたばかりの頃と比べると起きている時間は少し長く、睡眠にある程度リズムができてくるのもこの頃からで、「この時間はしっかり昼寝をしてくれる」というのがママの方でも分かりやすくなってきます。
授乳が終わった後も目がぱっちり開いているということも出てくるので、寝るまで抱っこを続けたりする必要もありません。
そのまま機嫌がいいようならベッドに置いて片付けや家事などに使える時間が多少出てくる時期です。
さらに上記の時間は平均的なものなので、まだまだ新生児の頃と変わらずリズムの出来ない赤ちゃんもたくさんいます。
だからといってママが慌てる必要は無く、赤ちゃんの個性だと思って付き合うことが必要です。
生後2ヶ月の赤ちゃんの睡眠時間が平均より短い時
赤ちゃんの個性である可能性も大いにあるのであまり神経質になりすぎる必要はありませんが、以下の理由も睡眠時間が短くなる理由として挙げられます。
どうしても赤ちゃんが寝ないことが気になる場合は参考にしてみてください。
赤ちゃんに必要な母乳の量が足りていない
ミルクで挙げる場合は赤ちゃんがどのくらい飲んだか明確にわかるのですが、母乳でお母さんがおっぱいから飲ませている場合は、赤ちゃんがどのくらい飲めているのか分かりません。
吸い付きが良いからしっかり出ているのかと思いきや、実は量が少なかったということもあります。
母乳の量は最初のうちは搾乳機を使って出ている量を明確にしておいた方が良いでしょう。
手動のだと手が疲れるので電動搾乳機がおすすめです。
- 母乳は冷凍保存できるので、しっかり1回分搾乳できればお父さんでも哺乳瓶から母乳をあげることが出来ますし、赤ちゃんが必要な量をきちんと飲めているのか目で確認できるようになります。
- お母さんの母乳の出が良くならなければ、ミルクに切り替える判断材料にもなるのでおすすめです。
まだ睡眠時間にリズムが出来ていない
赤ちゃんによっては早くから生活のリズムが出来る子もいれば、なかなか生活のリズムが定着しない子もいます。
母乳が特に問題ないようなら、まだそのリズムが出来上がっていないと見てあまり気にしなくても大丈夫です。
それでも朝はカーテンを開けて、夜は早めに暗くしてあげるというリズムは大事なので、なかなか定着しないと思っても根気強く続けましょう。
生後2ヶ月の赤ちゃんの睡眠時間が長すぎる時
それも個性なので特に無理やり起こす必要はありませんが、起こさなければいけない場合もあります。
以下に睡眠時間が長過ぎる赤ちゃんの注意すべき点を挙げていきます。
赤ちゃんの体重が増えていればOK
睡眠時間が長いということは、授乳やミルクの時間も短いということです。
よく寝る赤ちゃんもこまめに体重を測りましょう。これで体重がきちんと増えていなければ問題ありませんが、体重が増えていない場合、母乳が足りていません。
生後2ヶ月ほどでしたらまだ3~4時間に1回は授乳が必要なので、時間になったら起こして母乳をあげましょう。
おしっこの回数や量が少ないようなら起こして授乳
母乳やミルクが足りないとありがちなのが、おしっこの回数と量も減るというものです。
もしも寝る赤ちゃんでも、おしっこの量がしっかり出ているのであれば問題ありません。
大体生後2ヶ月だと1日15~20回ほど、1回の量で5~20mlほどのおしっこをします。
これよりも少ないようなら起こして授乳をしてください。
生後2ヶ月の赤ちゃんの睡眠リズムを整えるために出来ること
これをしたら必ず睡眠時間が整えられるという明確なものはありませんが、今後の生活リズムを作る上で大事な動作はあります。
生後2ヶ月なら思うような結果は得られないかもしれませんが、生後4~6ヶ月頃から生きてくる習慣もあるのでご紹介します。
朝起きる時間と夜の就寝時間はズラさない
これは赤ちゃんのうちから始めておくべき習慣です。
睡眠時間のリズムは一度定着したら直すのが大変です。最初から規則正しくしていれば後から苦労することはないので就寝時間のリズムはずらさないようにしましょう。
日中はコミュニケーションの時間を作る
赤ちゃんはお腹の中にいた頃からママの声をずっと聞いていたので、こまめに話しかけてあげるとリラックスできます。
リラックスできるとぐっすり眠れるので昼寝の時間がまとまってくるようになります。
入眠儀式を取り入れる
今すぐに役に立たない可能性が高いですが、今から初めておくのが大事なのが入眠儀式です。
入眠儀式とは寝る前に必ず行う行為であり、背中をトントンしたり絵本を読んであげたりと、その家庭で違います。
自分の続けやすい好きなことで構いません。
定着すると、赤ちゃんの生後半年くらいから入眠儀式をはじめて10分ほどでぐっすり寝てくれるようになるので寝かしつけが楽になります。
ママ自身の睡眠時間も上手に確保しましょう
まだママの睡眠不足な時期は続きます。
生後3ヶ月くらいまでは赤ちゃんがどうしてもまとまった睡眠がとれないので、まだママもしっかり寝られる時期は来ません。寝不足と上手に付き合っていくしかないので、この時期に出来る対処をご紹介します。
赤ちゃんが寝たらママもお昼寝タイム
赤ちゃんが寝たら自分も寝る、という流れをこの時期は優先的に作るようにしましょう。
家事は必要最低限にしないと、ママの体は休まりません。
ママがしっかり休めて食事も摂れていないと母乳にも影響が出ます。この時期の最優先は育児と自分の体なので、家族にどんどん手伝ってもらい、出来るだけ昼寝の時間を作りましょう。
夜だけはミルクを飲ませる
母乳はお腹が空きやすいので、夜に赤ちゃんが起きやすいです。
断乳の準備としてもおすすめなので、一日の終りに最後に飲ませるのは母乳ではなくミルクにしてみましょう。
ミルクは腹持ちがいいので夜中に起きにくくなります。